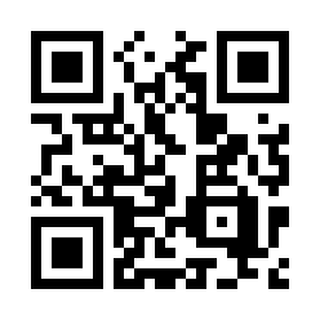24-25育成馬ブログ
難産で母馬を失った育成馬
〇繁殖牝馬の分娩後の死亡
二次診療への緊急の搬送を伴う疾病といえば疝痛が挙げられますが、生産地においては難産も重要な病気です。難産の発生率は約10%(McCue, 2012、Ginther, 1996)と言われており、その中でも親子の生死に関わるような獣医師を呼んで急患対応をしてもらう割合はすべての分娩の約3~4%(野村、2017および佐藤、2017)と報告されています。多くの症例においては、子馬よりも翌年以降もその血統を残せる可能性のある繁殖牝馬を救う対応が取られます。その結果、難産時の子馬の死亡率はすべての分娩の約1%(加藤、2017)であるのに対して、繁殖牝馬の死亡率は約0.4%(野村、2017)と報告されています。近年の生産頭数が約8000頭であるため、日本全体では年間で30頭程度の繁殖牝馬が難産時に死亡していると推定されます。
JRA日高育成牧場においても、難産において繁殖牝馬が死亡した症例に2023年に遭遇しました。この症例は、本来は伸びている胎子の両前肢や頭部が曲がってしまったタイプの難産で、全身麻酔下で胎子を引き出すこと(後肢吊り上げ整復)が必要となりました(写真1)。胎子の引き出しには約1時間半もの時間を要してしまい、この時点では誰もが胎子の生存は厳しいと感じていました。一般的に、分娩時間が30分を超えると、10分経過するごとに胎子の生存率も約10%低下することが知られています(Norton, 2007)ので、この状況は絶望的でした。
(写真1)後肢吊り上げ整復の様子
そのような状況でしたが、娩出された子馬は呼吸をしており、奇跡的に生存しており、すぐさま子馬の救命処置を開始しました。一時的に呼吸が弱くなる場面もありましたが、投薬処置により一命をとりとめました。一方、長時間の難産に苦しんだ繁殖牝馬は、産道の裂傷からの腸管脱出が認められ、子宮動脈破裂を疑うほどの出血があり、非常に厳しい状況でした。難産時に繁殖牝馬の死亡原因として、子宮動脈破裂が55%、腸管脱出が10%という報告(野村、2017)があり、二次診療施設で手術することを検討しましたが、残念ながら安楽死となりました。子馬のいななきに反応した母馬の姿は今でも忘れられません。生まれた子馬は母馬を失った子馬(Orphan Foal)として育てることとなりました(写真2)。
(写真2)母馬を失った子馬
〇人工乳の給与と乳母付け
母馬を失った子馬の管理では、いかにして栄養源を与えるかが重要となります。通常であれば母乳が栄養源となるわけですが、母馬を失った子馬は母乳を得られないので、代替となる栄養源が必要です。生産地では、馬用の人工乳が市販されており、ストック初乳の投与後は哺乳瓶を用いて人工乳を与えることになります(写真3、4)。通常の子馬は、最も多い時には30分に1回程度の頻度で吸乳しており、人工乳に関しても頻繁に与える必要があります。この子馬についても、2時間おきに与えました。また、量も1日で最大20L程度飲む時期もあります。以上のことから、哺乳瓶を用いた頻回給与には限界があり、ある程度のタイミングでバケツなどを用いて与える方法へ移行するのが現実的です。この子馬も11日齢からバケツや飼桶での給与を開始しました(写真4)。
(写真3)哺乳瓶による授乳
バケツであれば牧場スタッフの負担は軽減されますが、離乳までの長期間続けることは非常に負担です。また、生後からの親子での集団放牧がウマの性格や社会性の形成に重要な働きをしていると考えられています。例えば、子馬は母馬の行動(乾草を食べる、人の横を引き馬で歩くなど)を見てまねることで、色々な行動を早く学びます。さらに、他の親子と触れ合う中で個体間の上下関係を学び、人の指示に従う従順な性格となる下地ができるとも考えられています。以上のことから、母馬の代わりとなる存在がいることが理想であり、母乳の出る他の繁殖牝馬に育ててもらいます。これを『乳母付け』と呼びます。
一般的には、その年に出産した繁殖牝馬でないと母乳は出ませんが、様々な薬を投与することで、出産していない繁殖牝馬でも母乳が出るようになります。乳母に適した馬は、これまでに出産歴のある馬で、母性の強い馬が適していると言われています。今回は、6頭の出産経験があり、他の子馬の授乳も許容する空胎の繁殖牝馬を乳母にしました。このように温厚な繁殖牝馬であっても、いきなり授乳を許容するわけではありません。JRA日高育成牧場では分娩時の生理状態を再現する薬を投与し、乳母の状態を確認しながら乳母付けを行いました。乳母候補となる馬への処置が終わると、いよいよ子馬と対面させます。相性が悪いと子馬を蹴ったり、威嚇したりすることもあるのですが、今回の乳母と子馬は幸いにも、何事もなく授乳が許容されました。数時間もするとまさに本当の親子のような仲睦まじい姿となっていました(写真5~8)。
(写真5)乳母付けの様子【薬投与後】
(写真6)乳母付けの様子【子馬との対面】
(写真7)乳母付けの様子【授乳】
(写真8)本当の親子のように放牧地でまったり
なお、乳母付けなどについて詳細に知りたい方は、JRA育成牧場管理指針-生産編(第3版)-に記載されていますので、ダウンロードしてご活用ください。
〇母馬を失った馬の取扱いや育成
一般的に、母馬を失った子馬は取扱いが難しくなるというイメージが持たれています。これは、前述のように社会性の欠如が危惧されるからです。今回の子馬も、当歳時は少し他の子馬と距離があるような様子も見られましたが、乳母付けの効果もあり、その後は大きな問題もなく離乳や馴致を行っています。2歳となった現在は、坂路でハロン18秒を切るタイムでの調教も可能になっており、JRAブリーズアップセールに向け、順調に調整しています(動画1)。ぜひともこの育成馬に注目していただければ幸いです(写真9)。
(写真9)現在の姿(レディバゴ2023)