バイオメカニクス学会に行ってきました
こんにちは、運動科学研究室の高橋です。
昨年12月になりますが、中京大学豊田キャンパスで開催されたバイオメカニクス学会に参加してきました。
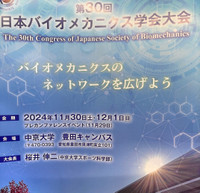
下の写真は屋内トラックでの企業展示とポスター会場の様子です。中京大学からは多くのオリンピック選手が卒業しており、スポーツに関する研究も非常に盛んです。この学会の対象は主にヒトになり、「身体運動に関する科学的研究と連絡共同を促進し、バイオメカニクスの発展を図ることを目的」とした学会になります。

筋電図に関する基調講演や走動作中の筋活動に関する演題も多数あり、ウマの筋活動を研究テーマの一つに挙げている運動科学研究室にとっては非常に参考になりました。一方で、脳科学との融合をテーマにした基調講演があり、MRIを使って特定の運動課題や認知機能に対する脳局所の反応を計測しているグループが、本番に強い人と弱い人では脳のどこが違うのかについて、アーチェリーを専門にしているアスリートを対象に計測した結果を紹介していました。すると本番に弱い選手(練習のスコアは良い選手)は本番に強い選手(本番のスコアが良い選手)に比べて島皮質という領域の体積が大きかったそうです。この他にも、特定の運動課題や認知機能に対する局所の反応を機能的MRIで計測し、その課題に対する脳の負荷を評価する手法により、ピアノを最後まで安定したリズムで継続できる人と途中でリズムが崩れてしまう人を運動開始時の脳の反応から予測することに成功しているそうです。私は大学の時、ラットの脳に関する研究を行っており、脳研究には元々興味があるのですが、運動パフォーマンス発揮時の「メンタル」というところまで踏み込んだ研究は初めて聞いたので非常に面白かったです。また、脳機能に関する研究は人工知能を用いてもたくさん行われており、動物が何を考えているのかもそのうち分かるようになるのではないかと夢が膨らんだ学会でした。
