【競馬学校】騎手課程26期生 入学前研修開始
寒い日が続きますね。その上空気の乾燥がひどく、静電気持ちとしては触るものみな「バチバチ」で不快な日々です。
そんな中、競馬学校は「来る人去る人」。まず来る人として、騎手課程(第26期生)入学予定者が、19日から研修を実施しています。研修は入学式(4月4日)の前日まで、2週間にわたり続きます。この間、休日はありませんので、事実上卒業の日までの、中央競馬の騎手になるための長く厳しい合宿鍛錬がスタートしたわけです。ちなみに、本日(20日)のスケジュールは、
5:40 起床・検量・点呼・体操
6:00 きゅう舎作業(管理馬 2頭)
7:00 朝食・休憩
7:30 きゅう舎作業(朝作業の残り)*寝藁返し・飼桶洗い等
8:00 装鞍
8:30 曳き馬
8:45 実技(乗馬訓練)
10:10 騎乗馬 手入れ(後は朝作業の残り)
11:00 きゅう舎作業(寝藁返し・ボロ取り・飼付)
12:00 昼食・休憩
13:00 きゅう舎作業(寝藁返し・ボロ取り・飼外し)
13:15 講義 馬具の手入れの仕方
14:30 講義 基本的生活態度 *あいさつ・お辞儀を中心に練習
16:00 きゅう舎作業(ボロ取り・掃き掃除・飼付等)
17:00 トレーニング
18:00 夕食・休憩
19:30 きゅう舎作業(ボロ取り・水変え・飼付等)
20:00 点呼・自由時間
22:00 消灯
となっており、後半の日程では実技で乗る鞍(馬)の数が増えていきますが、これは入学してからの生活とほとんど変わらないものとなっています。
また、今日は特に「あいさつ」や「お辞儀」の練習を入念に行いました。
 競馬学校テキスト「生徒の心構え」から、加藤和宏調教師が騎手時代の「人間的にも大事なことというのはまずはやはり礼儀、あいさつだ。僕らは一言あいさつしても聞こえないときは、何回でも相手が聞き返すまであいさつした。今の子供は小さく、もぞもぞと言って聞こえても聞こえなくてもいいや、そういうのがあるから、はっきりした態度でした方がいい。そうしないと相手も返ってこないから。そして今度自分が聞きたくとも相手が悪いとか何とかになると、やはり先輩たちも本当に教えてやろうということも教えなくなってしまう。」というお話を取り上げ、生徒たちへの教訓としました。
競馬学校テキスト「生徒の心構え」から、加藤和宏調教師が騎手時代の「人間的にも大事なことというのはまずはやはり礼儀、あいさつだ。僕らは一言あいさつしても聞こえないときは、何回でも相手が聞き返すまであいさつした。今の子供は小さく、もぞもぞと言って聞こえても聞こえなくてもいいや、そういうのがあるから、はっきりした態度でした方がいい。そうしないと相手も返ってこないから。そして今度自分が聞きたくとも相手が悪いとか何とかになると、やはり先輩たちも本当に教えてやろうということも教えなくなってしまう。」というお話を取り上げ、生徒たちへの教訓としました。
研修生は練習の後、事務所内を回ってあいさつの練習成果を披露していましたが、あ いさつとは人間関係のはじまり。馬に乗る技術を磨く以前に、基本的な礼儀作法から習得してもらうことは人として最も大事なことだと思います。(*写真については、正式入学前の研修生のプライバシーに配慮し、一部修正しております。ご了承ください。)
いさつとは人間関係のはじまり。馬に乗る技術を磨く以前に、基本的な礼儀作法から習得してもらうことは人として最も大事なことだと思います。(*写真については、正式入学前の研修生のプライバシーに配慮し、一部修正しております。ご了承ください。)
変わって去る人は、まず、きゅう務員課程の平成18年度10月生が卒業。色々と話題と個性派が多く、今後も我々の記憶に残るクラスでしたが、6か月のカリキュラムを終えて巣立っていきました。
東西のトレセンで、さらに立派なホースマンに成長してもらいたいものです。


また、中山グランドジャンプ・ペガサスジャンプステークスに出走予定のオセアニア馬4頭が、検疫を終え、中山競馬場に移動しました。写真左はノーヒーロー(NZ)のポール・ネルソン調教師。写真右のチェスに興じているのはリアルトニック(NZ)のブレット・クロージャー攻馬手。

 おかげさまで昨年中山グランドジャンプを勝たせてもらい、8月には05~06年の豪州ベスト障害馬に選ばれました。本国に帰国してからは休養させ、グランドジャンプの3連覇を視野に入れて調整してきました。その方法としては、ジャンプレースには使わず、平地の競走ばかりを使ってきました。最初短い競走から徐々に距離を延ばしていくやり方で、1月10日の復帰戦は1600m、以降1800m→2100m→2400m→3000m→2400mと平地戦ばかり使ってきました。これは、特に日本のスピード競馬を意識しているというわけではないのですが、結果的に効果が出ているのかも知れませんね。最高成績は3000m戦の4着でしたが、もちろん結果は気にしていません。
おかげさまで昨年中山グランドジャンプを勝たせてもらい、8月には05~06年の豪州ベスト障害馬に選ばれました。本国に帰国してからは休養させ、グランドジャンプの3連覇を視野に入れて調整してきました。その方法としては、ジャンプレースには使わず、平地の競走ばかりを使ってきました。最初短い競走から徐々に距離を延ばしていくやり方で、1月10日の復帰戦は1600m、以降1800m→2100m→2400m→3000m→2400mと平地戦ばかり使ってきました。これは、特に日本のスピード競馬を意識しているというわけではないのですが、結果的に効果が出ているのかも知れませんね。最高成績は3000m戦の4着でしたが、もちろん結果は気にしていません。  うちのきゅう舎では、カラジや一緒に連れてきたパーソナルドラム(10歳)のような10歳以上の高齢馬が10頭ぐらいいるのですが、若い馬と区別して取り扱っているわけではありません。ただ、歳をとるとステップレースをむやみに走らせることはしませんね。あえて言えば、体調面や精神状態を常に把握してあげることが大事なのではないでしょうか。大事に取り扱ってさえいれば、競走馬の寿命というものは、ある程度長くすることはできると思います。
うちのきゅう舎では、カラジや一緒に連れてきたパーソナルドラム(10歳)のような10歳以上の高齢馬が10頭ぐらいいるのですが、若い馬と区別して取り扱っているわけではありません。ただ、歳をとるとステップレースをむやみに走らせることはしませんね。あえて言えば、体調面や精神状態を常に把握してあげることが大事なのではないでしょうか。大事に取り扱ってさえいれば、競走馬の寿命というものは、ある程度長くすることはできると思います。 我々もプロですし(笑)、3年続けて来日してますので、検疫期間中の生活も慣れていますのでご心配なく。NZ勢も2頭おり、食堂では毎日賑やかにやってますよ。日本の食べものも大変おいしい(日本食では刺身、特にツナ(マグロ)とサーモンが好物だとのことです)。注文をつけるとすれば放牧場がもう少し広ければ…というくらいでしょうか。
我々もプロですし(笑)、3年続けて来日してますので、検疫期間中の生活も慣れていますのでご心配なく。NZ勢も2頭おり、食堂では毎日賑やかにやってますよ。日本の食べものも大変おいしい(日本食では刺身、特にツナ(マグロ)とサーモンが好物だとのことです)。注文をつけるとすれば放牧場がもう少し広ければ…というくらいでしょうか。





 他にマスグローヴきゅう舎のパーソナルドラム(せん10歳)。また、ニュージーランド勢のリアルトニック(せん11歳)とノーヒーロー(せん11歳)が来日。4頭ともいわゆる前哨戦のペガサスジャンプステークス(中山・3月24日)に出走予定で、20日までの検疫期間中は競馬学校で調教をしていくことになります。
他にマスグローヴきゅう舎のパーソナルドラム(せん10歳)。また、ニュージーランド勢のリアルトニック(せん11歳)とノーヒーロー(せん11歳)が来日。4頭ともいわゆる前哨戦のペガサスジャンプステークス(中山・3月24日)に出走予定で、20日までの検疫期間中は競馬学校で調教をしていくことになります。 藤岡康太騎手は、3日(土)の中京1R、ヤマニンプロローグで史上42人目の「初騎乗・初勝利」(JRAの創設は昭和29年ですので、昭和30年以降の記録となります。下に42名全員をあげておきました。)大変立派な記録ですし、直線も良く追えましたが、4コーナー手前で外斜行して、過怠金50000円を科せられたのはいただけません。ちょっとした判断ミスによる走行妨害をすれば、レースは台無しになり、他の馬は勿論、馬券を買っていただいているファンの皆さまに多大な迷惑をかけることになります。本人談にもありますように、これからもフェアプレー第一で伸びていってほしいと思います。ちなみに写真右の片山研きゅう務員は競馬学校きゅう務員課程の18年度7月生で、担当馬の初勝利。勿論馬と合わせて三重の喜びとなりました。おめでとうございます。(写真提供:オボ山さま)
藤岡康太騎手は、3日(土)の中京1R、ヤマニンプロローグで史上42人目の「初騎乗・初勝利」(JRAの創設は昭和29年ですので、昭和30年以降の記録となります。下に42名全員をあげておきました。)大変立派な記録ですし、直線も良く追えましたが、4コーナー手前で外斜行して、過怠金50000円を科せられたのはいただけません。ちょっとした判断ミスによる走行妨害をすれば、レースは台無しになり、他の馬は勿論、馬券を買っていただいているファンの皆さまに多大な迷惑をかけることになります。本人談にもありますように、これからもフェアプレー第一で伸びていってほしいと思います。ちなみに写真右の片山研きゅう務員は競馬学校きゅう務員課程の18年度7月生で、担当馬の初勝利。勿論馬と合わせて三重の喜びとなりました。おめでとうございます。(写真提供:オボ山さま)
 田中健騎手は同日中京6Rで、10番人気のメイショウセレットで直線大外一気の追い込みで初勝利。単勝7630円と波乱の立役者に!4コーナーを向いて追い出す姿は「ムササビの如し」。懸命に追った甲斐があったネ。ケンちゃん。後で聞いたら藤岡の初勝利に刺激を受けたようで、「早いうちに何とか初勝利を、そのためにはひと鞍ひと鞍が勝負」と意気込んでいたそうです。
田中健騎手は同日中京6Rで、10番人気のメイショウセレットで直線大外一気の追い込みで初勝利。単勝7630円と波乱の立役者に!4コーナーを向いて追い出す姿は「ムササビの如し」。懸命に追った甲斐があったネ。ケンちゃん。後で聞いたら藤岡の初勝利に刺激を受けたようで、「早いうちに何とか初勝利を、そのためにはひと鞍ひと鞍が勝負」と意気込んでいたそうです。

 写真左:大下智騎手、写真右:濱中俊騎手 結果は出なかったがまだまだこれから。
写真左:大下智騎手、写真右:濱中俊騎手 結果は出なかったがまだまだこれから。

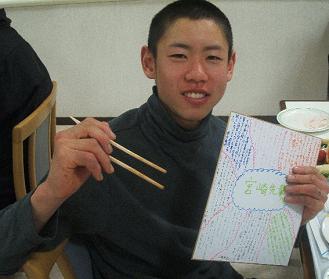 乗馬経験がほとんどなく、実技試験の成績は下の方が続いていたのですが、その分人より努力した結果、2年生の期末試験の走路騎乗で1位が取れたのが一番の思い出です。それから
乗馬経験がほとんどなく、実技試験の成績は下の方が続いていたのですが、その分人より努力した結果、2年生の期末試験の走路騎乗で1位が取れたのが一番の思い出です。それから 【本人より】競馬学校での生活は長くて長くてイヤでした。卒業した今ではもっと教わりたかったと思っていますが。22期生時代から成績は下の方でしたから、負け犬根性が染み付きそうだった時もありましたし、実技でうまくいかないときに教官から、雰囲気が似ている?せいか、「コラ!ラーメン屋!」と怒られたときにはブチ切れそうになったこともありました。でもぐっと呑み込んで、くさらずにやってきてよかったです。
【本人より】競馬学校での生活は長くて長くてイヤでした。卒業した今ではもっと教わりたかったと思っていますが。22期生時代から成績は下の方でしたから、負け犬根性が染み付きそうだった時もありましたし、実技でうまくいかないときに教官から、雰囲気が似ている?せいか、「コラ!ラーメン屋!」と怒られたときにはブチ切れそうになったこともありました。でもぐっと呑み込んで、くさらずにやってきてよかったです。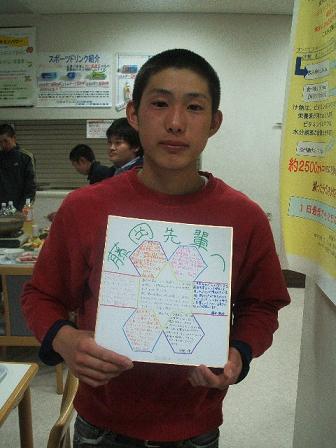 【本人より】入学前から栗東トレセンの乗馬センターで5年間乗っていましたので、少しは自信があったのですが、入学してすぐに先生から「お前はギリギリで合格したんだぞ」と言われショックを受けました。確かに背中が丸いとか、ひざで締め過ぎているとか欠点を指摘され、馬になるのが段々つらくなる時期がありました。毎日毎日頑張ってきてそのうちに「姿勢よりも技術でうまくなってやろう」と欲が出てきました。走路騎乗の実習は楽しくて仕方がなかったのですが、ある日、3周も馬を御せずに持って行かれたうえ、強風で無線機からの教官の指示が良く聞き取れずこっぴどく叱られたのは忘れられません。
【本人より】入学前から栗東トレセンの乗馬センターで5年間乗っていましたので、少しは自信があったのですが、入学してすぐに先生から「お前はギリギリで合格したんだぞ」と言われショックを受けました。確かに背中が丸いとか、ひざで締め過ぎているとか欠点を指摘され、馬になるのが段々つらくなる時期がありました。毎日毎日頑張ってきてそのうちに「姿勢よりも技術でうまくなってやろう」と欲が出てきました。走路騎乗の実習は楽しくて仕方がなかったのですが、ある日、3周も馬を御せずに持って行かれたうえ、強風で無線機からの教官の指示が良く聞き取れずこっぴどく叱られたのは忘れられません。 こうして卒業できて思うのは、色んな方に会えて幸せ者だなということです。栗東トレセンでも、阪神タイガースの濱中治選手と名前が似ているので、すぐに名前を覚えてもらいました。ちなみに私の誕生日は、ちょうどオグリキャップが最初に有馬記念を勝った日なんです。競馬が好きな両親がテレビで有馬記念を見ていると、母親が急に陣痛を起こして、それでもレースは最後まで見るんだと頑張って、レースが終わってから病院に駆け込んで生まれた子なのだそうです。その時から競馬との縁があったんですね。騎手になって、テレビで見られる身になるわけですが、「濱中乗れないなぁ…」と皆さんにボヤかれないように頑張りますので、応援よろしくお願いします。
こうして卒業できて思うのは、色んな方に会えて幸せ者だなということです。栗東トレセンでも、阪神タイガースの濱中治選手と名前が似ているので、すぐに名前を覚えてもらいました。ちなみに私の誕生日は、ちょうどオグリキャップが最初に有馬記念を勝った日なんです。競馬が好きな両親がテレビで有馬記念を見ていると、母親が急に陣痛を起こして、それでもレースは最後まで見るんだと頑張って、レースが終わってから病院に駆け込んで生まれた子なのだそうです。その時から競馬との縁があったんですね。騎手になって、テレビで見られる身になるわけですが、「濱中乗れないなぁ…」と皆さんにボヤかれないように頑張りますので、応援よろしくお願いします。