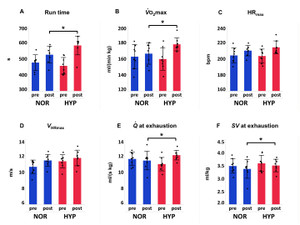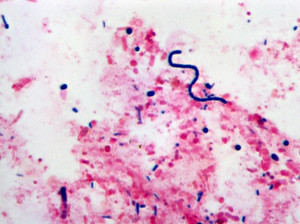新人獣医師を対象とした研修が始まりました。
臨床医学研究室の田村です。
新人獣医師を対象とした研修が始まりました。
普段は両トレーニング・センターの競走馬診療所で臨床獣医師として勤務していますが、専門的な知識や技術を習得するために、競走馬総合研究所に出張して来ました。
例年は6月頃に実施していますが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響があり、10月からのスタートになりました。
先日のブログにおいて、学会にWeb参加したことを紹介しましたが、この研修も一部にWeb講義を取り入れています。写真はフランスに留学中の先輩獣医師から、薬の使用方法について説明を受けているところです。双方向での会話が可能であり、研修生は講義後も熱心に質問をしていました。

JRAでは新人獣医師を対象にした研修の他にも、多数の研修を実施しています。知識や経験を新しい世代にしっかりと引き継ぐ体制を整えています。
研修期間はおよそ2週間です。熱いエールをお願いします。



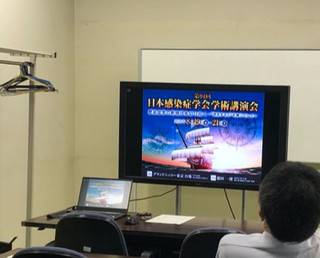
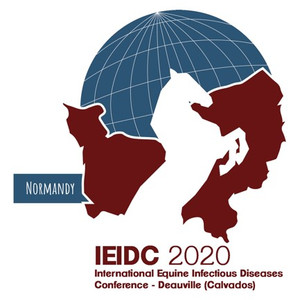







 仲間を心配そうに見つめています。自分も刈られる覚悟を決めているのでしょうか。
仲間を心配そうに見つめています。自分も刈られる覚悟を決めているのでしょうか。
 「ん~~、スッキリ!」といった表情でしょうか。
「ん~~、スッキリ!」といった表情でしょうか。
 ガロンヌ川
ガロンヌ川 ベルーガ
ベルーガ 大学正面
大学正面 乗馬センター
乗馬センター 放牧馬
放牧馬