競走馬医療の秘密基地 ~臨床医学研究室とは?~
臨床医学研究室の石川です。
皆さん、競馬を見ていると、馬がケガをしたり体調を崩したりすることがありますよね。そんな時、「早く元気になって、またターフを走ってほしい!」と願うファンの方は多いはず。
実は、そんな競走馬たちの健康を守り、最先端の医療でサポートしている、「競走馬医療の秘密基地」それが、「臨床医学研究室」です。
この研究室の最大の目標は、ケガや病気で走れなくなった競走馬を、再びレースに復帰させること。
「どうしたら、もっと早く、確実に治るんだろう?」
「そもそも、どうやったらケガを予防できるんだろう?」
を日々研究し、医療技術向上に向けた取り組みをしております。
中でも運動器疾患の診断、予防、治療の開発に関する研究に力を注いでいます。近年では高度な画像診断によって、骨折や腱靱帯炎を早い段階で発見することができるようになり、レースや調教中の大きな事故が少なくなりました。MRIやCTといった人で使用される機器を応用することで、診断技術の向上に役立てています。 MRI検査(四肢専用) CT(手術専用)
MRI検査(四肢専用) CT(手術専用)
また、競走馬には「屈腱炎」と呼ばれる競走生命を脅かす病気があります。人で例えるとアキレス腱断裂と似たものですが、長年、効果的な治療法が見つかっていません。そうした中で人で注目を浴びている再生医療(幹細胞や多血小板血漿)の研究に着手し、現在ではリハビリテーションを含めた効果について研究を行っています。
その他には、抗菌薬や各種治療薬の効果的な投与法や、さまざなま病気の治療に関するカルテを分析し、最適な予防や治療法の検討を行っています。
こうした研究室で生まれた研究成果がJRAのトレーニングセンターにいる競走馬の獣医師へと共有され、臨床現場の医療技術を向上させています。
我々臨床医学研究室は、競走馬の健康を支えるいわば「縁の下の力持ち」なのです。

 B&B館内にはたくさんの馬や写真が飾られていました
B&B館内にはたくさんの馬や写真が飾られていました
 時差ぼけもありましたが、アイリッシュコーヒーに負けて眠れなくなりました
時差ぼけもありましたが、アイリッシュコーヒーに負けて眠れなくなりました





 獣医師による講義に集中する子供たちの面々
獣医師による講義に集中する子供たちの面々 馬の扱い方についての講義
馬の扱い方についての講義 トレッドミル上で馬の走りを実演
トレッドミル上で馬の走りを実演 乗馬体験では事故がないよう細心の注意が払われる
乗馬体験では事故がないよう細心の注意が払われる


 (左)会議プログラムと(右)肺オルガノイドに関する講演の様子
(左)会議プログラムと(右)肺オルガノイドに関する講演の様子 (左)オープンディスカッションと(右)懇親会の様子。フランス語と英語が飛び交って交流が交わされた。
(左)オープンディスカッションと(右)懇親会の様子。フランス語と英語が飛び交って交流が交わされた。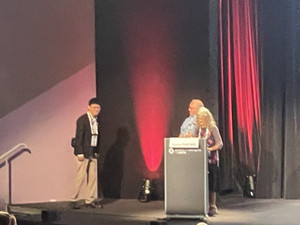 表彰式で演台に呼ばれる筆者
表彰式で演台に呼ばれる筆者