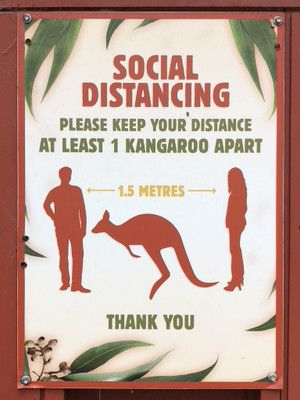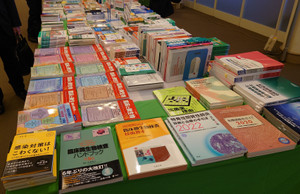アメリカスポーツ医学会@デンバー
運動科学研究室の向井です。
5月30日から6月2日にアメリカ・コロラド州デンバーにあるコロラド・コンベンションセンター(写真1)にて開催されたアメリカスポーツ医学会(ACSM)の年次総会(写真2)において、運動科学研究室から私と胡田が研究発表を行いました。ACSMは世界最大のスポーツ医学および運動科学の学会で、科学・教育・医学を通じて健康を推進させることをスローガンにしています。
https://www.acsm.org/annual-meeting/annual-home(外部リンク)
日本の獣医学関連の学会ではスポーツ科学に関する発表はあまりありません。ACSMはヒトの学会ですが、ヒトのスポーツ医学の国際学会に参加することによって、最先端のスポーツ医学から多くのことを学べます。そればかりか、我々の研究を国際的に評価してもらえるメリットがあるのです。
今回、私はサラブレッドにトレッドミル上で6週間の高強度インターバルトレーニングを実施させると、同じ距離で中等度の持続的なトレーニングをするよりも走行パフォーマンス、有酸素能力および乳酸代謝が向上、さらに筋線維の肥大が見られることを発表しました。高強度インターバルトレーニングとは、早いスピードの運動と遅いスピードの運動を交互に繰り返すトレーニングを意味します。実際の競走馬に応用するとなると、馬の気性や調教コース設定などにより、その走強度やインターバルの設け方など様々な工夫が必要ですが、近い将来、調教メニューの選択肢のひとつになる可能性があります。
一方、胡田は暑熱環境下でサラブレッドに運動をさせると、骨格筋におけるミトコンドリアやエネルギー代謝に関わる因子が増加することを発表しました。これらの因子はサラブレッドの暑熱耐性や運動パフォーマンスの改善に関与している可能性があります。近年JRAでは、競馬場にシャワーやミストを設置するなど、競走馬の暑熱対策に積極的に取り組んでいます。暑熱環境下でウマの体に何が起きているのかを研究することによって、科学的な根拠に基づいてより効果的な暑熱対策が可能になると考えています。

写真1.コロラド・コンベンションセンターは、非常に目立つ巨大オブジェ;Blue bearで有名。
ビルを押し動かしているかの如きBlue bearは遠くからでも見え、目印になります。

写真2.学会のウエルカム・ボードの向こうに受付会場が展開

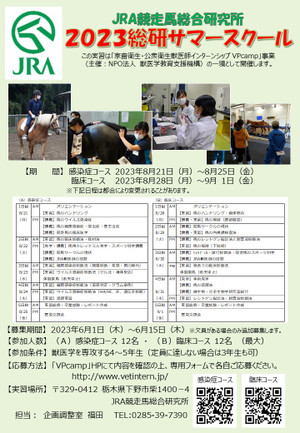
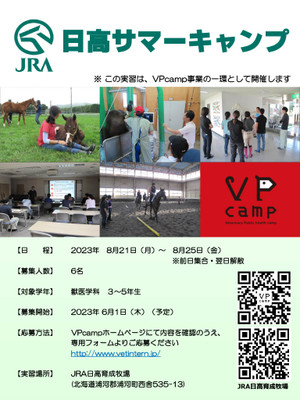

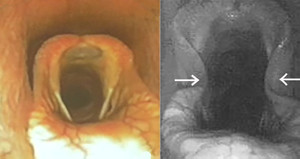
 図1. 馬の黒目は水平な棒状をしています
図1. 馬の黒目は水平な棒状をしています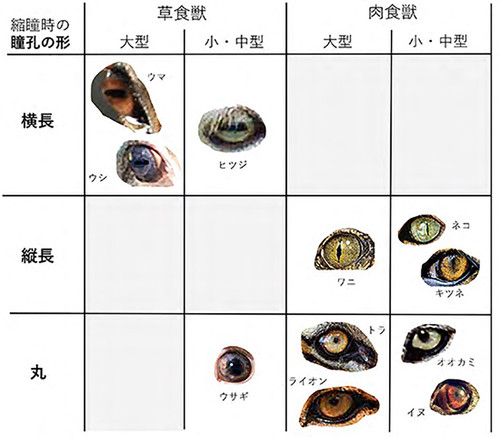



 学会が開催されたマンチェスター中央会議場
学会が開催されたマンチェスター中央会議場 古さと新しさが同居した街、マンチェスター
古さと新しさが同居した街、マンチェスター マンチェスターといえば、なんといってもサッカーですね。
マンチェスターといえば、なんといってもサッカーですね。