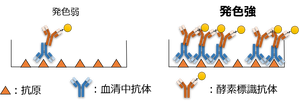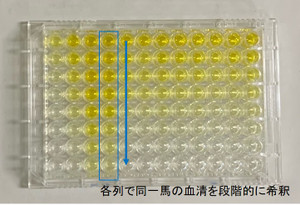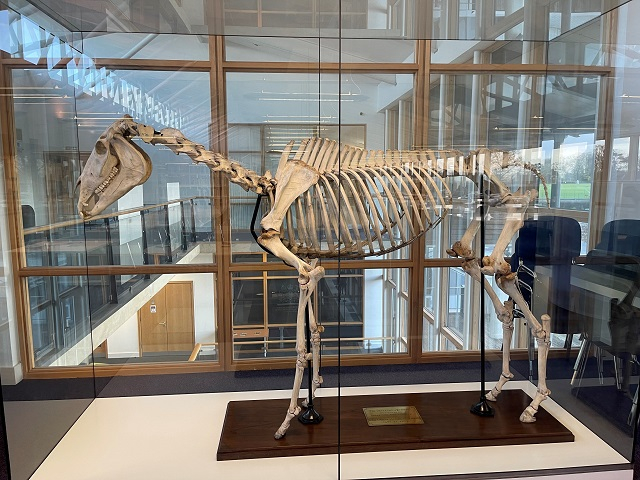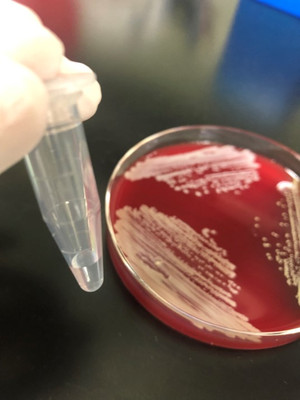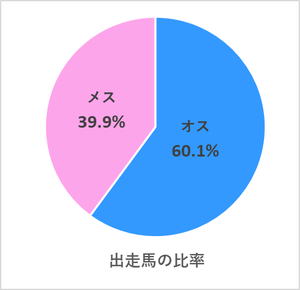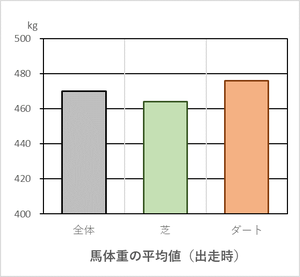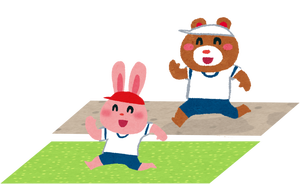ルイジアナダービー
こんにちは。微生物研究室の越智@ルイジアナ州です。
日本では春のG1シーズンが始まりました。ご存知の通り,私の留学しているアメリカも競馬の盛んな国です。ルイジアナ州には,Fair Grounds Race Courseがあります。この競馬場は1838年に開場し,現存する競馬場としては米国で2番目に古い競馬場として知られています。今回, G2ルイジアナダービー(3歳,ダート9.5ハロン)を見るべく,弊社ニューヨーク事務所の職員と同競馬場に赴きました。ルイジアナダービーは,G1ケンタッキーダービー出走馬選定ポイントシリーズにカウントされており,過去の勝ち馬がケンタッキーダービーで好走することも多いようです。
 ダービーの日はドレスコードが設定され,多くの人がドレスアップしている
ダービーの日はドレスコードが設定され,多くの人がドレスアップしている
 ルイジアナダービーのレイ。ケンタッキーダービ同様,バラの生花で作られている
ルイジアナダービーのレイ。ケンタッキーダービ同様,バラの生花で作られている
以前に紹介したように,当研究所の獣医職職員は競馬場での業務も担当しています(ブログ(外部リンク))。初めてみたアメリカの競馬・競馬場は,本会とは異なるところもありとても楽しめました。
 事故救護用の救急車(奥)とピックアップトラック(手前)。トラックには,万が一に備えて遮蔽幕が常備されている。
事故救護用の救急車(奥)とピックアップトラック(手前)。トラックには,万が一に備えて遮蔽幕が常備されている。
パドックでマイクロチップを読み取る係員(左側)
上の写真↑をクリックするとgoogle drive(外部サイト)につながり動画が再生されます。
ファンファーレは途中からジャズの名曲に(各レースで異なるアレンジのようです)






 タイガースタジアム@ルイジアナ州立大学
タイガースタジアム@ルイジアナ州立大学