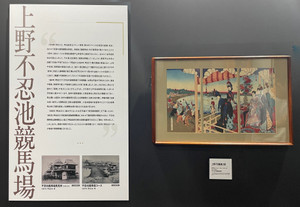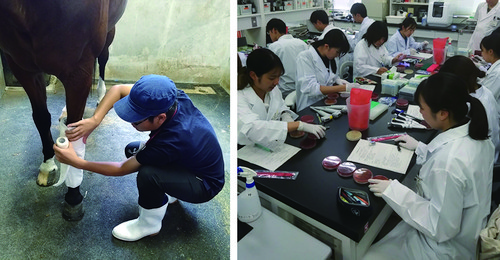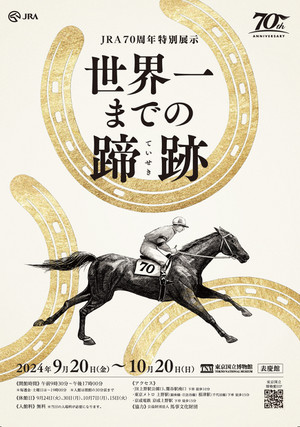シマウマの真似して吸血昆虫から馬を守る
企画の杉田です。
最近、競走馬総合研究所(総研)に来た数頭の馬は、白と黒の縞々の馬服を着せられて放牧されています(写真1)。

写真1.シマウマ馬服を着た馬
随分と風変わりな馬服で、違和感を持つ人もいるかもしれませんが、この縞々にアブやらサシバエのような吸血昆虫を寄せ付けない効果があるのをご存知でしょうか(参考1)。この効果は色々な調査・実験によって証明されています。
例えば、野生のシマウマとインパラの毛皮を用いたサシバエの集り実験(参考2)では、明らかな差をもってシマウマの毛皮の方が単色のインパラの毛皮よりサシバエを寄せ付けなかったことが報告されています。 また、黒色和牛に皮膚色より濃い黒い縦縞、あるいは白い縦縞を書いて放牧した実験(参考3)では、白い縦縞を何本も書かれた和牛の方が何も書かれていない和牛や黒縞が書かれた和牛よりも、取り付くサシバエの数が少なく、また、ハエを追い払おうとする行動の頻度も少ないというデータが報告されています。
ハエやアブは、匂い、形、動き、明るさ、色、偏光、体温によって宿主動物に引き寄せられますが、白黒の縞模様はさまざまな誘引要素を遮って吸血昆虫を遠ざける効果があるようです。おそらく昆虫の眼が、この色と模様に惑わされて着地点を認識しにくくなるためと考えられています。
このような吸血昆虫を寄せ付けない効果を狙って、シマウマ模様の馬服が開発されたようですね。防虫剤の効果は長く続きませんし、薬によっては馬に害となるものもあるでしょう。こういった自然の力を利用した方法は、馬の福祉にもつながる良い戦略ではないでしょうか。
参考1(外部リンク)
https://company.jra.jp/equinst/magazine/pdf/69-2019-3.pdf
参考2(外部リンク)
https://www.nature.com/articles/s41598-022-22333-7
参考3(外部リンク)
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0223447&type=printable










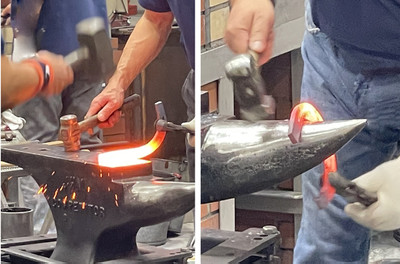
 図1.東京国立博物館の表慶館
図1.東京国立博物館の表慶館