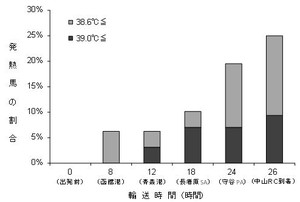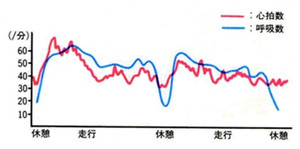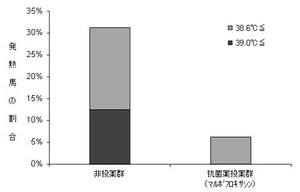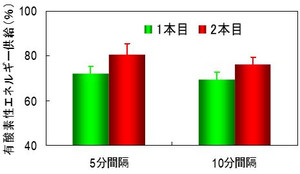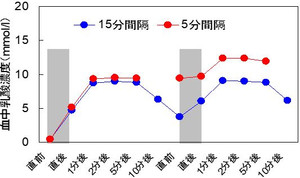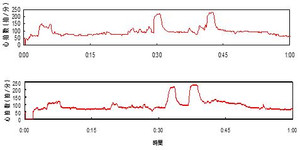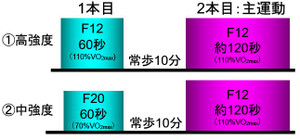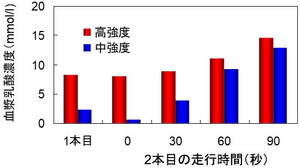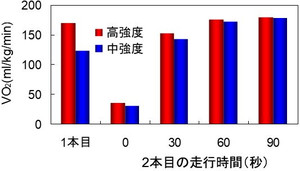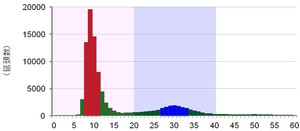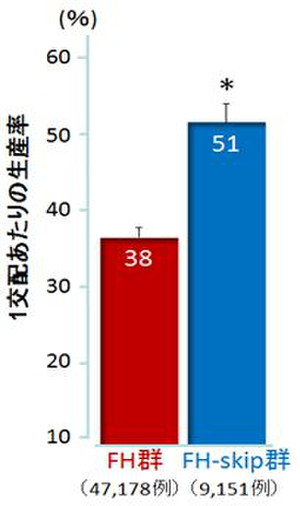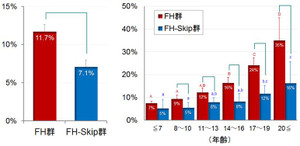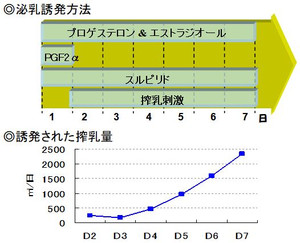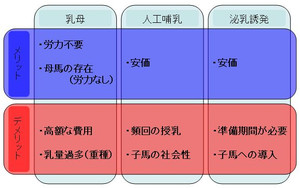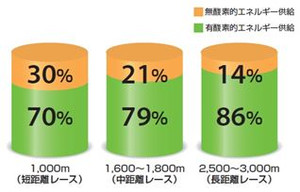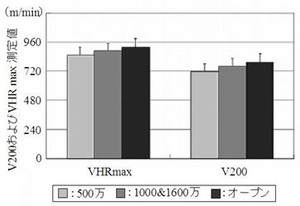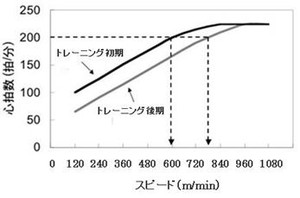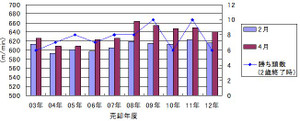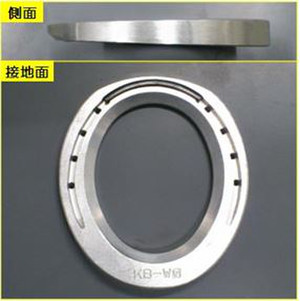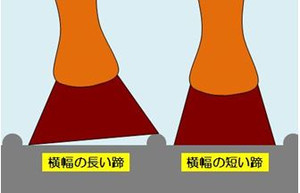ブリーズアップセールで取組む「新規馬主のセリ市場参入促進策」
No.76 (2013年4月15日号)
4月23日(火)、中山競馬場で2013 JRAブリーズアップセール(第9回JRA育成馬調教セール)を開催いたします(写真1)。前日の4月22日(月)には、事前に実馬をじっくり吟味いただけるよう、前日展示会も開催いたします。今年も、皆様のご来場を心からお待ち申し上げております。
JRAでは、ブリーズアップセール(以下BUセール)を、育成研究に用いたJRA育成馬を売却する場としてだけでなく、新規に馬主免許を取得された方やセリでの購買に慣れていない方が、本セールをきっかけに、他の多くの市場へ興味を拡げていただけるような“入門編のセール”と位置づけています。したがって、参加される皆様がBUセールを通して「セリに参加する楽しさ」を味わっていただき、市場の活性化につなげたいと願っています。本稿では、2013 JRAブリーズアップセールを通して実施する“新規馬主のセリ市場参入促進への取組み”についてご紹介します。
(写真1) 昨年のBUセールの様子
1)「セリと育成馬を知ろう会」の開催
新規に馬主免許を取得された方には、「セリで馬を購買したいが参加の仕方がわからない」、「馬を選定する際のポイントを知りたい」、「調教師との接点がほしい」などの要望があります。これらニーズの解決の糸口になればと、昨年10月17日(水)および18日(木)にHBA北海道市場および馬事部生産育成対策室が中心となり日高育成牧場のJRA育成馬を活用して“セリと育成馬を知ろう会inひだか”を実施しました。当日は、新規馬主3名およびその同伴者1名が来場しました。日高育成牧場では、「馬の見方」、「馬の生産そして育成から競走馬までのライフサイクルの説明」等、実際にJRA育成馬を展示しながら解説しました(写真2)。また、懇談をかねた夕食会では、一般社団法人 日本調教師会(以下日本調教師会)の協力により、オータムセールに参加していた調教師2名が参加し、新規馬主が調教師とのコンタクトをとる方法を説明していただく等、有意義な時間をすごすことができました。翌日は、オータムセールを実際に見学し、セリの流れやレポジトリーの見方等、購買までの流れを体験していただきました。
(写真2)実馬を用いて馬の見方を解説しました(JRA日高育成牧場)
先月3月15日(金)および16日(土)には“セリと育成馬を知ろう会in宮崎”を開催しました。気候が温暖で交通の便が良い宮崎は、3月中旬にイベントを開催するのに適しています。新規馬主7組が宮崎育成牧場に来場され、さわやかな気候の下、イベントをお楽しみいただきました。まず、「馬の見方」を講義した後、BUセールに上場する馬を全頭展示 (写真3)するほか、調教も見ていただきました。日本調教師会の協力を得て6名の調教師にも参加いただき、夕方の懇親会では馬主・調教師および馬主の方同士の交流が和やかに行なわれ、調教師と接点が少なかった参加馬主の皆様には大変好評でした。
(写真3)上場馬全頭の展示を行ないました(JRA宮崎育成牧場)
2)新規馬主オリエンテーションの開催
馬主の皆様がセリ市場に参加しやすい環境づくりを目的として、新規に馬主登録をされた方を対象に、「新規馬主オリエンテーション」を1月26日に実施しました。JRA競走関連室馬主登録課が中心となり馬事部生産育成対策室がサポートする形で、馬主協会、調教師会の協力を得て東京競馬場で開催しました。昨年馬主登録をされた馬主16名およびその同伴者11名、また、6名の調教師が参加しました。当日は実際に競馬観戦を楽しみながら、「馬主活動について」、「馬主協会の概要」「全国セリ市場やBUセールの案内」や「馬の見方等、セリに活かせる馬の基礎知識」などの説明を行ないました。次回は6月に実施する予定です。
3)馬主・調教師懇談会の開催
日本調教師会では、BUセール前日の展示会当日(4月22日11:30~12:30)に、購買登録をされた馬主の方を対象に、中山競馬場事務所2F会議室において調教師との懇談会を予定しています。これは、調教師との面識の有無に関わらず、調教師にとって大切な顧客である馬主の方に対して、BUセールでの購買のみならず預託を希望される調教師への橋渡し等、馬主活動のさまざまなサポートをしていくことを目的としています。懇談会後は前日展示会(13時から装鞍所において)に参加していただく予定となっています。
4)新規馬主限定セッションの開催
昨年同様、JRAホームブレッドの売却を新規馬主の方(2010年1月以降に馬主登録された方)に限定して実施します。今年は、まず、新規馬主の方にセリに参加していただこうという趣向の元、限定セッションをセリの最初に準備いたしました。今年は、ファーストクロップサイヤーランキング2位のアルデバラン産駒8頭(牡3頭、牝5頭)を上場することとしています。なお、限定セッションでは、多くの新規馬主の皆様に馬を所有していただくチャンスを広げるため、お一人1頭のみの購買制限を行わせていただきます(限定セッション上場馬が「調教進度遅れとして上場された場合」および「限定セッションで売却されず再上場された場合」は、全馬主が参加可能となり、購買頭数の制限はございません。詳しくは名簿をご覧ください)。
BUセールは今年の市場を占うバロメーター
BUセールはトレーニングセール第1弾として、今年の市場全体を占うバロメーターとなることから、活気あるスタートを切る大きな責任があると考えています(写真4)。BUセールでは、5月から行われる民間の2歳トレーニングセールや夏の1歳市場の主催者ブースを設ける予定としておりますので、来場いただいた皆さまに是非活用いただきたく願っています。BUセールをきっかけに、新規馬主をはじめ多くの来場された皆様が“セリで馬を買おう!”という雰囲気になってくれることを願っています。
本年も、来場された皆様がセリを楽しんでいただけるよう、また、これまでどおり、皆様の信頼を失わないよう、セリ運営に取組んで参ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
(写真4)BUセールでの騎乗供覧[サウンドリアーナ号:ファンタジーS(GⅢ)]
(日高育成牧場 業務課長 石丸 睦樹)